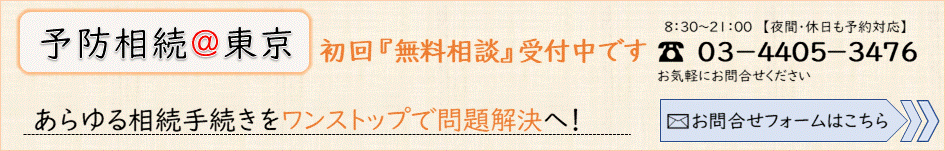受付時間 | 8:30~21:00(時間外・休日も対応いたします:要予約) |
|---|
公正証書遺言と自筆証書遺言の比較~自筆証書の最大の弱点とは・・??
『公正証書遺言と自筆証書遺言どちらがよいのだろう!?』
遺言には大きく分けて公正証書遺言と自筆証書遺言があります。それぞれに特徴があるため、どちらの形式で遺言を残した方がよいのかと悩まれる遺言者様も多いと思います。遺言を残そうとお考えいただいている目的は、残された家族が相続問題で揉めたり困らないようにということではないでしょうか。どちらの形式を選択いただいても相続問題の予防という効果はありますので、基本的にはご自身に合っている方を選択いただければ良いと思います。
しかし、私たち予防相続@東京にご相談いただく遺言者様には、公正証書遺言を選択することをおススメしています。それは自筆証書遺言には、公正証書遺言にはない最大の弱点があるためです。両形式についての基礎知識から実務における事例紹介もいたしますので是非ご参考にしていただければと思います。
【目次】
1.公正証書遺言と自筆証書遺言の比較表
2.自筆証書遺言の最大の弱点
3.事例紹介
4.まとめ
1.公正証書遺言と自筆証書遺言の比較
公正証書遺言と自筆証書遺言の特徴を簡単な表にまとめます。まずは、それぞれの特徴をご確認ください。
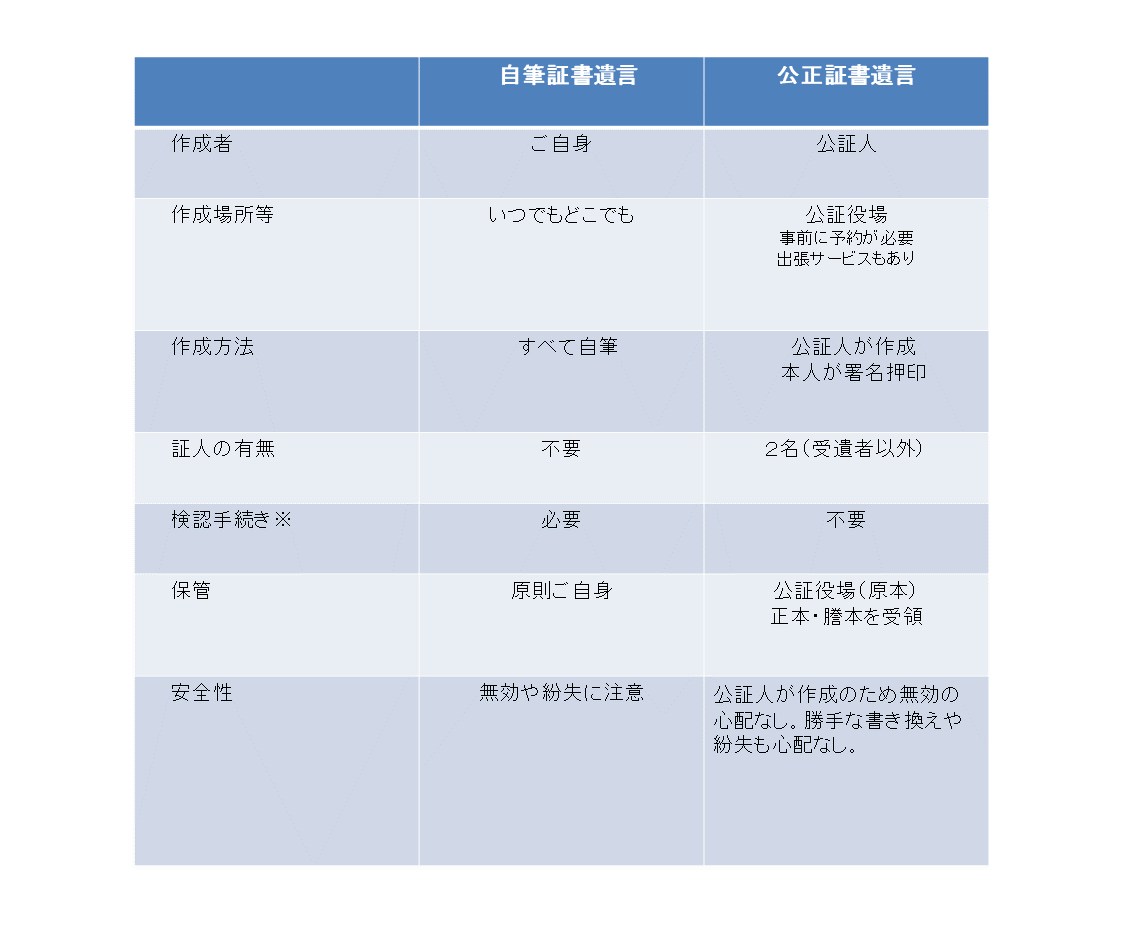
《公正証書遺言と自筆証書遺言に共通の基礎事項》
・書き換え(作り直し)はいつでも可能。全体でも一部でもOK。
・公正証書と自筆証書に優劣はなし。後の日付の遺言が前の遺言に優先して効力をもつ。
・受遺者(遺言によって財産をもらう者)が先に亡くなったら無効。受遺者としての権利は相続しない。
2.自筆証書遺言の最大の弱点
自筆証書遺言はいつでも簡単に費用をかけず残せるという大きなメリットがあります。その一方で、効力についての不安や保管についての不安といったデメリットもあります。しかし、効力や保管については、専門家のチェックを受けたり、銀行の貸金庫に保管したりと対処すればリスク軽減は可能です。では自筆証書遺言の最大の弱点とは何でしょうか?それは民法に定められた検認という手続きをしなければいけないということです。
【検認とは・・・】
自筆証書遺言について家庭裁判所で検査確認をとる手続きです。検認手続きが終わるまでは、当該遺言に基づいて相続手続きをすることが出来ません。また検認では遺言書の様式・内容の有効性を確認するわけではありません。
次の事例で具体的な検認手続きについてや何故それが最大の弱点となるのかをご確認ください。
3.事例紹介
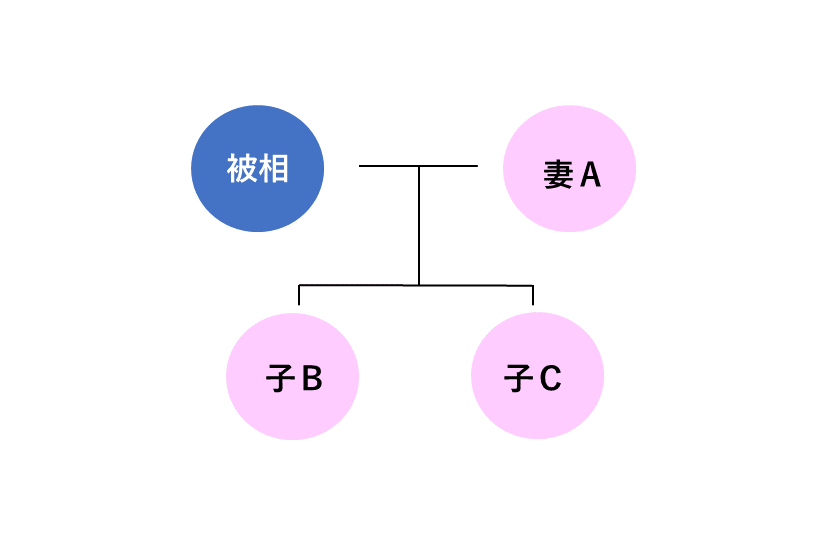
【事例1】法定相続人の間で不満が生じるような場合
法定相続人は妻A、子B、子C
被相続人及び妻Aは、子Cと意見の対立から絶縁状態となり数十年間連絡もとっていませんでした。そのため、同居している子Bが二人の介護や身の回りの世話をしてくれていました。被相続人は妻Aと子Bに財産を残したいと考え、『不動産(土地と家)を妻Aに2分の1、子Cに2分の1相続させる』旨の自筆証書遺言を残しました。
このような事例ではどのような手続きが必要となるでしょうか?それでは早速ご説明していきましょう。
繰り返しになりますが、自筆証書遺言に基づいて相続手続きをするには必ず検認が必要となります。そこで、まずは検認のため(法定相続人確定のため)に戸籍等の収集をします。
《必要戸籍等》
□被相続人の出生から死亡までの「戸籍・除籍・改製原戸籍」
□妻A、子B、子Cの「現在戸籍」
□妻A、子B、子Cの「住民票(戸籍の附票)」※裁判所に当事者目録を提出するため
次に、法定相続人が確定しましたら被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に自筆証書の検認の申立てをします。検認の手続きで注目すべき点は、家庭裁判所から法定相続人全員に遺言があった旨及び遺言の内容確認のため立ち会うようにと連絡がいくという点です。つまり絶縁状態である子Cにも連絡がいくということです。
検認手続き自体は相続人全員が揃わなくても行われるため、子Cが立ち合いに来なくても(来ないなら)問題はありません。検認が済めば遺言書に基づきて不動産の名義変更ができます。しかし、子Cが遺言の内容を知ったため遺留分(最低限保障されている相続分)の請求をしたり、遺言自体の無効を主張したりすれば手続きが停滞してしまうことが考えられます。
なお、公正証書遺言では検認の手続きは不要ですので、遺言に基づいた相続手続きをすぐにしていただけます。その場合子Cを手続きに関与させる必要は一切ありません。子Cは遺留分の請求はできますが、相続開始後10年(亡くなったことを知って1年)の請求できる期間には制限があります。
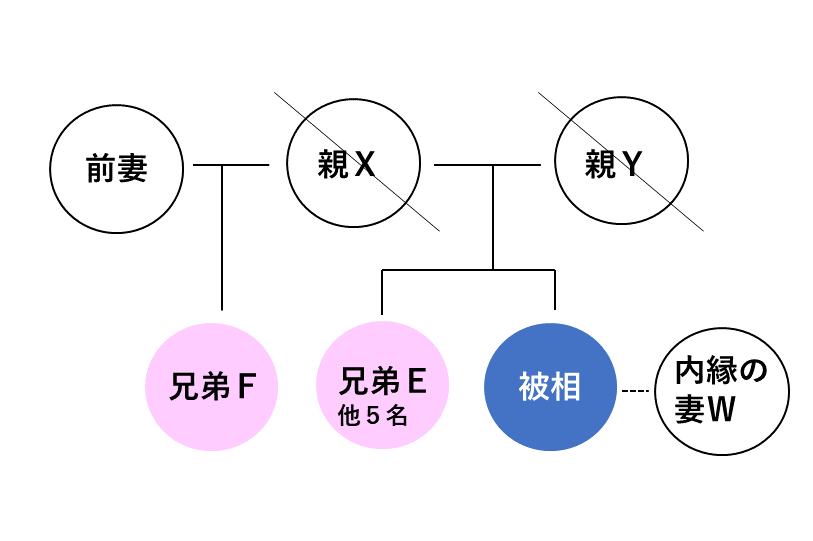
【事例2】法定相続人が多数いる場合
法定相続人は兄弟姉妹E、F、他5名
被相続人は、内縁の妻Wに財産を残したいと考え、『遺産の全てを内縁の妻Wに遺贈する』旨の自筆証書遺言を残しました。
このような事例ではどのような手続きが必要となるでしょうか?
事例1同様、まず戸籍を収集し相続人を確定し、自筆証書遺言について検認を受ける必要があります。
《必要戸籍等》
□被相続人の出生から死亡までの「戸籍・除籍・改製原戸籍」
□親X、Yの出生から死亡までの「戸籍・除籍・改製原戸籍」
□兄弟姉妹E、F、他5名の「現在戸籍」
□兄弟姉妹E、F、他5名の「住民票(戸籍の附票)」※裁判所に当事者目録を提出するため
兄弟姉妹間の相続の場合、法定相続人確定のための戸籍が大量になることが多く、収集に要する時間も1カ月以上となってしまうことがあります。兄弟姉妹に遺留分はありませんので、遺言の検認が終われば問題なく遺言に基づきお手続きできます。しかし、兄弟姉妹から遺言の有効性について異議があった場合はもちろん、戸籍収集だけを考えても時間がかかってしまう点に注意が必要です。銀行の預貯金払戻し等が凍結してしまい長期間できなくなってしまうといったようなことが生じます。
なお、公正証書遺言であれば、すぐお手続き可能です。兄弟姉妹には遺留分がないため気にする必要がなく、戸籍を収集する必要もありません。
4.まとめ
□公正証書遺言と自筆証書遺言に優劣はなし。原則自分に合った方を選択すればOK。
□自筆証書遺言の最大の弱点は『検認』が必要になるということ。
□公正証書遺言ならすぐに手続きが可能。